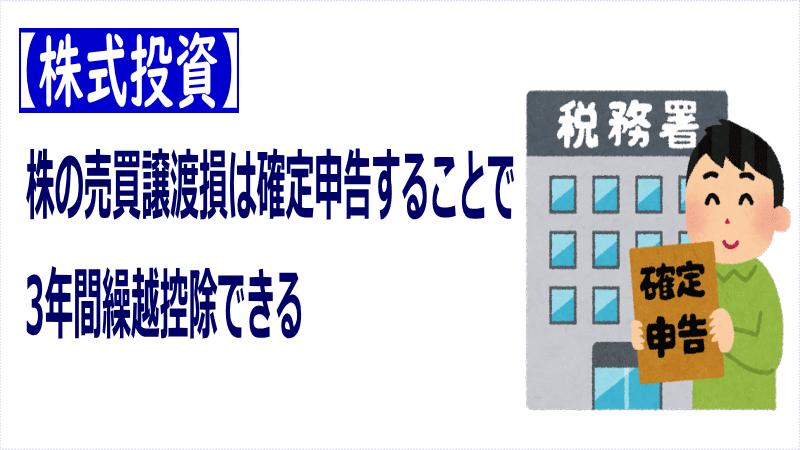株式投資では損失が発生する可能性もあります。特に初心者のうちは、株の売買は想像以上に難しいため、受け取る配当金以上に譲渡損失が多くなることも少なくありません。
今回は、株式投資によって損失が出た場合に確定申告することで、将来的な節税につながる「3年間の繰越控除」のメリットと注意点を解説します。
株式投資と確定申告
株式投資をしている個人投資家の多くは、証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」で口座開設していると思います。
特定口座(源泉徴収あり)で口座開設している限り、確定申告は義務ではありません。利益に対して一律20.315%の税率で所得税(復興特別所得税含む)・住民税を自動的に納税してくれます。わざわざ面倒な確定申告をする必要がないのは大きなメリットです。
しかし、確定申告は納税のためだけでなく、時には救済措置として利用できる場合があります。株式投資における3年間の繰越控除も確定申告における救済措置の一つです。
3年間の繰越控除とは?
3年間の繰越控除とは、株式投資における譲渡損失を確定申告することで翌年から3年間、その損失額を控除として利用できる制度です。
簡単に言えば「譲渡損失を確定申告しておけば、向こう3年間の株の利益に対する税金を相殺できますよ」ということです。
例えば、100万円の譲渡損失を繰越控除して、翌年に100万円の譲渡益が出た場合に確定申告をすれば、損失と利益が相殺されるため税金がかかりません。
特定口座(源泉招集あり)だからと言って何もしなければ、約20万円の税金が徴収されることになるので大きな違いになります。
譲渡損失の3年間繰越控除のポイント
この損失の繰越控除ですが、詳細は国税庁のサイトから確認できます。
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm
繰越控除の要点だけまとめると次の通りです。
- 譲渡損失を確定申告する
- 翌年以降も続けて確定申告する
- 譲渡益がない年も譲渡損失を3年間繰り越すための申告が必要
繰越控除は確定申告することで適用される
繰越控除を適用する期間はずっと確定申告が必要になります。期間内に確定申告をしない場合には、その後に繰越控除を適用することは出来ません。
| ケース | 申告と控除の有無 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事例A | 確定申告 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 繰越控除の適用 | – | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 事例B | 確定申告 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 繰越控除の適用 | – | 〇 | × | × |
※事例Bでは3年目に確定申告をしていないので4年目に確定申告をしても、繰越控除が適用されない
国保加入者は合計所得が増加する場合には注意
また、繰越控除額よりも、それを適用するために確定申告する利益の方が多い場合には合計所得が増加します。
例えば、繰越控除額が100万円あり、それを適用するために確定申告する株式投資の利益が200万円だった場合には、控除後に100万円の利益が残るため合計所得が増加することになります。
合計所得は、国民健康保険料の算定に影響します。合計所得が増加することで、国民健康保険料が増加する可能性があります。
ですから、損失を繰越控除していても申告する利益が控除額よりも大きい場合、合計所得への影響を考える必要があります。
| 内容 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 |
|---|---|---|---|---|
| 年間譲渡損益 | -300万円 | +100万円 | +150万円 | +150万円 |
| 繰越控除残額 | – | 300万円 | 200万円 | 50万円 |
| 控除利用額 | – | 100万円 | 150万円 | 50万円 |
| 控除後の合計所得 | 0円 | 0円 | 0円 | 100万円 |
「特定口座(源泉徴収あり)」なら合計所得は増加しない
株の利益を確定申告することで合計所得も増加しますが、「特定口座源泉徴収あり」の口座で確定申告をしなければ、合計所得に影響はありません。
そのため、確定申告をしなければ繰越控除は適用できませんが、合計所得は増えることはありません。
【まとめ】繰越控除は翌年以降の利益額に注意して利用する
譲渡損失の繰越控除は、節税対策として非常に魅力的な制度です。
しかし、繰越控除を適用後に残る利益がある場合には、合計所得への影響に対する注意が必要です。