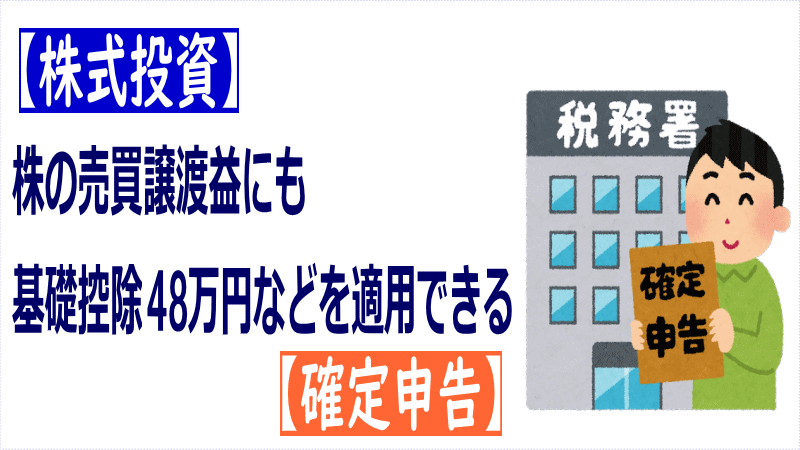確定申告では申告分離課税になる、株式投資の売買譲渡益に基礎控除などの控除が適用できることについて解説します。
株の売買譲渡損益は申告分離課税
申告分離課税は、他の所得と合算せず独立して税額を計算する課税方式です。
一方で総合課税は、給与所得など総合課税の対象となる所得を合算して、それに対して税額を算出します。(日本の所得税は累進課税)
株式投資による売買譲渡益は、この申告分離課税で確定申告することになります。
配当金は総合課税と申告分離課税を選択できる
株式投資の損益は、配当金または譲渡損益の2種類です。
配当金に関しては総合課税でも、譲渡損失と合算する形で申告分離課税で確定申告することも可能です。
株の譲渡損益を申告分離課税で申告するケース
株式投資の売買譲渡益は必ず確定申告が必要ではありません。確定申告が義務である場合、確定申告が任意である場合があります。
※以下は配当金を考慮せず譲渡損益のみで考えた一例です
確定申告が義務である場合
一般口座では所得の計算から納税まで、自分で行う必要があります。また、特定口座でも源泉徴収しない口座では、納税は自分で行う必要があります。
そのため、「特定口座(源泉徴収あり)」以外の口座利用者は、株式投資の売買譲渡益があれば確定申告が必要です。
確定申告が任意である場合
「確定申告が任意である」というのは確定申告することでメリットがある人で、具体的に次のような人がそれにあたります。
- 一般口座、特定口座に関わらず譲渡損失が出ている人
- 譲渡損失の繰越控除を適用する人
- 総合課税の所得が低く、基礎控除などが余る人
上記のような人は申告する義務はありませんが、申告することで還付や控除が適用される可能性があります。
今回の株式投資の売買益に対する基礎控除の利用は、この中で3番の総合課税の所得が低く、基礎控除などが余る人が対象になります。
申告分離課税でも基礎控除が利用できる理由
基礎控除は、合計所得金額に応じて適用される控除で、合計所得金額が2400万円以下の人で所得税は48万円、住民税では43万円の基礎控除が受けられます。(令和6年1月現在)
国税庁のサイトに「確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つに基礎控除があります。」と記載されています。
この「総所得金額等」には申告分離課税の所得である株式投資の売買譲渡益も該当します。※改正等ありますので、正確な情報は国税庁のホームページを参照してください
国税庁|基礎控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
基礎控除は総合課税から優先して適用される
ただし、基礎控除は総合課税から優先して適用されます。つまり、総合課税の所得が48万円以上になると所得税の基礎控除は全額適用されていることになります。
ですから、株式投資の売買譲渡益以外の収入が少ない場合において、基礎控除が利用できることになります。
例えば、一時的に無職で株式投資の譲渡益以外に収入がない場合などが考えられます。この場合、他の所得に基礎控除を使うことがないので、申告分離課税である売買譲渡益にも基礎控除が適用されます。
基礎控除以外にも所得控除は株の譲渡損益に適用できる
また、財務省のサイトのデータを基に考えれば、基礎控除以外でも所得控除(の一部?)は株の譲渡益にも適用されるようです。
参考ページ
財務省|所得税の基本的な仕組み
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/b01.htm
上記のホームページなどの記載から、社会保険料控除など他の控除も株式投資の売買譲渡益に適用可能だと判断できます。
※ただし、私自身が全ての控除を受けているわけではありませんので、申告する場合は税務署等に確認してください。
【まとめ】基礎控除等の所得控除が余るなら確定申告を検討する
控除がどこまで利用できるかは曖昧な点もありますが、総合課税による所得を差し引いても基礎控除や所得控除が余っているのであれば、特定口座で源泉徴収していても、確定申告を検討する価値はあると思います。
一番簡単な確認方法は、国税庁の「e-Tax」を利用して自分の収入や適用できる控除などを試算することです。私の場合は基礎控除の他に社会保険料の控除が適用できました。
また、この記事は主に所得税に関して言及していますので、住民税についてはお住まいの自治体に問い合わせてください。