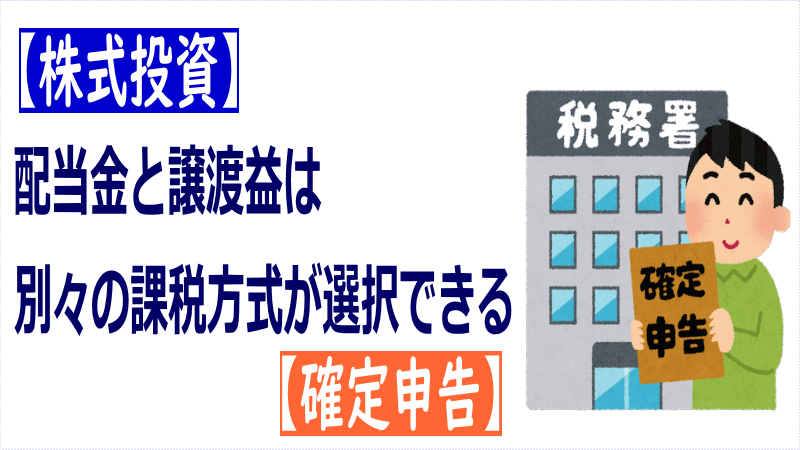株式投資で利益が発生していても、特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば、配当金や譲渡益は確定申告は不要です。しかし、確定申告をすることでメリットがあるなら確定申告をすることもできます。
今回は、株式投資の配当金と譲渡損益の課税方式について解説します。
株式投資の利益と課税方式
株式投資における利益は配当金と譲渡益です。税法上、この2つは別の所得として扱われます。
特に配当金は確定申告をする場合に、総合課税と申告分離課税を選択することができます。対して、譲渡益は申告分離課税のみ申告が可能で、総合課税は選択できません。
総合課税とは
総合課税は課税方式のひとつで、複数の所得を合算して課税額を計算する仕組みです。給与所得や事業所得、配当所得が総合課税になります。
所得税における総合課税は累進課税ですから、所得が高い部分ほど税率が高くなります。一方で住民税の総合課税では一律10%の税率です。
申告分離課税とは
申告分離課税は課税方式のひとつで、他の所得とは別にその所得のみで課税額が算出される仕組みです。
株式投資の配当金や譲渡益を申告分離課税で申告すると、所得の金額に関わらず一律20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)の税率で課税されます。
配当金と譲渡損益では別々の課税方式を選択することが出来ます。というより、次の2択になります。
配当金を総合課税、譲渡損益を申告分離課税で確定申告
配当金を総合課税で申告すれば配当控除が適用できる
配当金を総合課税で確定申告することで配当控除の適用が可能です。
配当控除では、課税所得が1000万円以下の場合に所得税で10%、1000万円を超える場合には5%の控除が適用されます。(※住民税は課税所得1000万円以下で2.8%、1000万円を超える場合には1.4%)
そのため、課税総所得が695万円以下の場合は、総合課税で申告した方が配当金にかかる税金が安くなる可能性があります。
詳細記事:【株式投資】配当金は総合課税と申告分離課税を選択できる【確定申告】

国民健康保険加入者は注意
国民健康保険料は各自治体が住民税の申告内容を基に算出されます。そのため、課税総所得が695万円以下の場合でも、配当控除額よりも保険料負担が大きくなりデメリットになる可能性があります。
配当金を総合課税で申告すると損益通算が出来ない
ただし、配当金を総合課税で申告した場合には損益通算ができません。
損益通算とは譲渡損失を、配当金や別の証券口座の譲渡益と共に申告分離課税で申告することで、損失分の還付を受けられる仕組みです。
損益通算は確定申告しない場合や、総合課税で申告した配当金には適用されません。配当金を損益通算を適用するためには、申告分離課税で確定申告しなければいけません。
【まとめ】配当金の課税方式は慎重に選択しよう
特定口座(源泉徴収あり)を利用している個人投資家が、確定申告をした方が得になるかは、ケースバイケースです。
特に、配当控除を適用するために配当金を総合課税で申告するのであれば、所得金額や国民健康保険の加入の有無などによっても、メリット・デメリットが大きく変わります。
手間はかかりますが、確定申告をする前に専門家への相談や試算をしっかり行うことがオススメです。