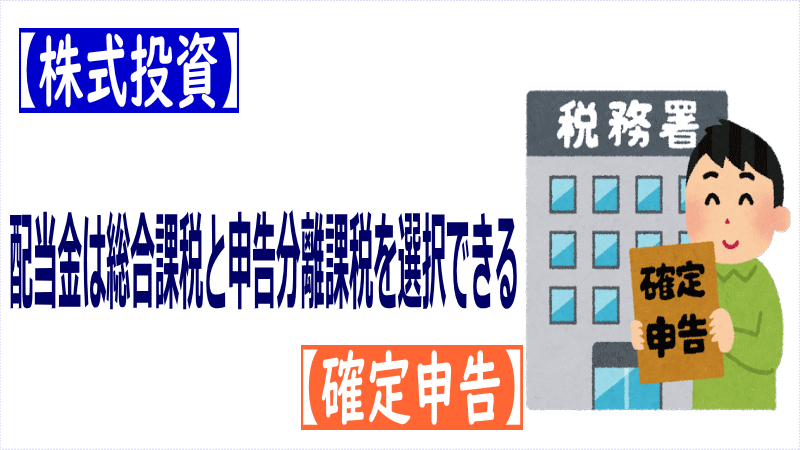今回は、配当金を確定申告する場合は、総合課税と申告分離課税を選択できること、それぞれの課税方法を発生するメリットや注意点について解説します。
「特定口座(源泉徴収あり)」で口座を開設している人は、損益の計算や配当金・譲渡益にかかる税金の支払いも、証券会社が自動的にやってくれるため確定申告をする必要はありません。
しかし、譲渡損失が発生した場合や所得が低い場合には、確定申告をすることで控除や損益通算が適用され還付が受けられる場合があります。
配当金と確定申告
配当金は株主に対して行われる利益や剰余金の還元です。
配当金は譲渡損益と違って必ず所得になるので、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座を利用している個人投資家は確定申告が必要になります。※給与所得者の副業等の所得20万円以下の場合は除く
配当金は総合課税と申告分離課税を選べる
配当金は確定申告で、総合課税と申告分離課税を選択することができます。※譲渡損益は申告分離課税のみ
では、総合課税と申告分離課税ではどのような特徴があるのでしょうか。
配当金を総合課税で申告する
総合課税とは、各種の所得金額を合計して所得税額を計算するというものです。 個別で税率を定めて課税するのではなく、所得の合計に対して税率が定められています。
総合課税制度|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2220.htm
配当金を総合課税で確定申告する最大のメリット「配当控除」があることです。
配当控除とは
配当とは日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、証券投資信託の収益の分配などで、確定申告において総合課税の適用を受けた配当所得に限られます。※外国法人から受ける配当等は、配当控除の対象となりません
配当控除の計算
上場株式に対する配当控除は以下の通りです。
課税総所得1000万円以下の部分
- 所得税・・配当所得の金額×10%
- 住民税・・配当所得の金額×2.8%
課税総所得1000万円超の部分
- 所得税・・配当所得の金額×5%
- 住民税・・配当所得の金額×1.4%
詳細は国税庁のサイトで確認してください。
配当所得があるとき(配当控除)|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1250.htm
総合課税で確定申告するポイント
配当金を総合課税で申告するメリットは、配当控除により税率が20.315%を下回るかどうかがポイントです。
20.315%は特定口座や申告分離課税で申告した場合の税率です。この税率の内訳は、所得税15%、復興特別所得税0.135%、住民税5%です。
配当控除を利用することで、この税率を下回るなら納税額は少なくなります。
総合課税の税率は所得税では累進課税ですから、所得が多いほど配当金の税率は高くなります。※住民税は一律10%
所得695万円以下なら配当控除がお得に
結論から言えば、配当金を総合課税する場合、課税総所得が695万円で特定口座や申告分離課税よりも税率が低くなります。
この所得を超えると、総合課税では配当金にかかる税率が20.315%を超えるため、特定口座で源泉徴収するか申告分離課税で確定申告した方が得になります。
また所得が330万円以下の場合には所得税は10%以下になるために配当控除により所得税は0%になり、住民税の7.2%を考慮しても配当金にかかる税率は低くなります。
参考:税率早見表|大和証券
http://www.daiwa.jp/seminar/study_tax/tax_rate.html
課税所得の増加で他の影響が出る可能性
上で解説したように税率だけで考えれば、課税総所得が695万円以下であれば配当金の総合課税での確定申告はメリットがあります。
しかし、課税所得が上がることで、配偶者控除や扶養控除の資格喪失や、国民健康保険料が値上がりする可能性があります。
そのため、特定口座で源泉徴収する場合に比べて、総合的な負担金額が多くなるかもしれません。
確定申告する際は、課税所得の上昇による影響を検討する必要があります。
配当金を申告分離課税で申告することで損益通算ができる
申告分離課税で確定申告する場合は、配当金の税率は特定口座で源泉徴収される税率と変わりません。
ただし、別の証券口座で譲渡損失が出ている場合には、配当金を利用して損益通算することができます。
譲渡損失と配当金を申告分離課税で申告すれば、譲渡損と配当益が相殺されることで、配当金にかかる税金の還付が受け取れます。
課税所得の増加は総合課税で申告する場合と同様
また、申告分離課税で確定申告しても課税総所得が増加することは総合課税と同様です。
配当金の方が譲渡損失よりも多い場合には、損益通算した残りの所得は課税所得となり、各種控除や国民健康保険料に影響があります。
【まとめ】配当金は確定申告した方がメリットがある場合が多い
特定口座で源泉徴収している個人投資家でも、課税所得が低い場合は確定申告をする方がメリットがあるかもしれません。
扶養控除や配偶者控除などを利用している人や国民健康保険加入者などでは申告しない方が良い場合もありますが、株式投資をしている個人投資家はが確定申告をすればどうなるかを調べてみてはいかがでしょうか。