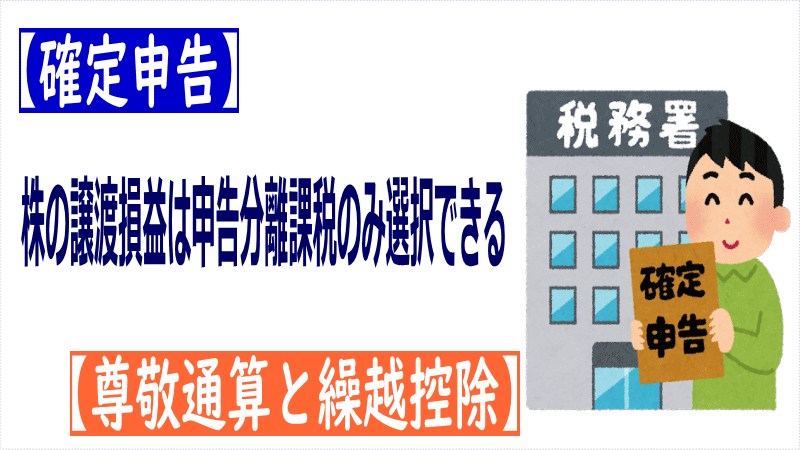今回は、株式投資の譲渡損益を確定申告する時は、申告分離課税しか選択できないこと、確定申告することで発生するメリットや注意点について解説します。
株式投資では「配当金」という利益と「譲渡損益」という損益があります。
配当金は、株主への利益還元であるため損失になることはありません。しかし、譲渡損益は買値と売値の差であるため、利益になるか損失になるかは売買次第です。
配当金と譲渡損益は確定申告時の課税方式にも違いがあります。
譲渡損益は申告分離課税で申告する
配当金が総合課税と申告分離課税を選択できる一方で、株の売買譲渡損益は申告分離課税のみ選択可能です。
申告分離課税では、所得の種類ごとに税率が定められています。株式投資に係る売買譲渡損益は利益(所得)に対して所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%と税率が一律で定められています。
申告分離課税は税率20.315%
つまり申告分離課税における株の譲渡益に対する税率は20.315%(住民税含めて)ということになります。※譲渡損失の場合には課税されません。
申告分離課税における税率は、特定口座で源泉徴収される場合でも同様です。
「特定口座(源泉徴収あり)」で証券口座を開設しているなら、確定申告の必要もなく、税率も同様なら一見すると確定申告するメリットはないように思います。
しかし、確定申告をすることでメリットになる場合があります。
申告分離課税で確定申告するメリット
申告分離課税で株の譲渡損益を確定申告するメリットは、譲渡益と譲渡損失を損益通算できることです。
損益通算とは、ある特定口座では譲渡益になっていて、別の特定口座では譲渡損失が発生している場合に、両口座の損益を合算することです。
特定口座(源泉徴収あり)では、その口座内においてのみ譲渡損益の計算を行い、税金を徴収されます。
確定申告をして複数の証券口座の損益を通算をすることで、過払いになっている税金の還付を受けることができます。
また、譲渡損失は確定申告することで、その先の3年間に渡って損失額を繰越控除することも可能です。
申告分離課税がメリットになる事例
申告分離課税によってメリットになる事例は次の通りです。
- 複数の証券口座の利益と損失を損益通算する場合
- 配当金と株の譲渡損失を損益通算する場合
- その年の損失を繰越控除する場合
- 総合所得が少なく基礎控除などが利用できる場合
1~3は、譲渡損失を損益通算して還付を受けるための確定申告です。
4に関しては、株式投資以外の所得が低く基礎控除が余っている場合には、申告分離課税である売買譲渡益についても控除による還付が受けられるということです。
申告分離課税で確定申告するデメリット
申告分離課税で確定申告するデメリットは、合計所得が高くなる可能性があることです。
特定口座(源泉招集あり)を利用して確定申告をしない場合には、合計所得には影響しません。
しかし、申告分離課税で申告すれば、損益通算後の利益は合計所得に含まれます。(損益通算してもマイナスなら合計所得は増えません)
合計所得が増えれば国民健康保険料が上がる
国民健康保険加入者の場合、合計所得が上がることで保険料が増加する可能性があります。
そのため、国民健康保険加入者の場合には、合計所得についても検討する必要があります。
【まとめ】申告分離課税は状況に応じて利用しよう
株式投資をしている個人投資家は、特定口座(源泉徴収あり)で口座を開設している人が多いと思います。
特定口座(源泉徴収あり)では、確定申告が不要になるメリットがありますが、譲渡損失を出した時や他の所得が低い場合には、確定申告をした方が良い場合もあります。
所得状況に応じて、譲渡損益について申告分離課税による確定申告をするか検討してみましょう。