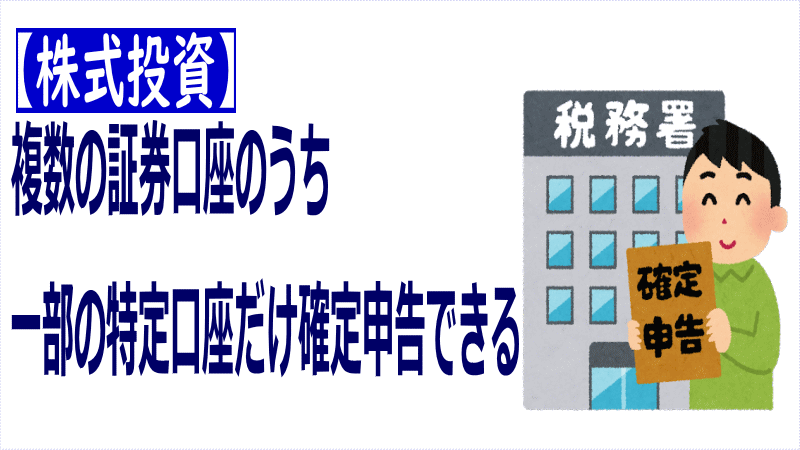「特定口座(源泉徴収あり)」で複数の証券口座を開設していても、全部ではなく一部の証券口座だけを確定申告できることやそのメリットについて解説します。
複数の証券会社で「特定口座の源泉徴収あり」の口座を開設している人は、損益の計算や配当金や売買譲渡益にかかる税金の支払いも、各証券会社が自動的に行うため確定申告をする必要はありません。
しかし、節税のために配当金や譲渡損益を確定申告したい場合には、確定申告をすることが出来ます。この際の確定申告は、必要な特定口座だけを確定申告することが可能です。
特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告した方がいいケースと理由
確定申告が面倒なので「特定口座(源泉徴収あり)」を選択したのに、改めて確定申告をする理由は何でしょうか。その理由は、もちろん「節税」ですね。
特定口座で源泉徴収する場合、配当金と売買譲渡益に一律で20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)課税されます。
しかし、特定口座では1社の証券口座内における所得だけで源泉徴収額が決定するため、他の所得と相対的に考えると必要以上に源泉徴収されていることがあります。
確定申告をした方がいい事例
特定口座で源泉徴収していても、確定申告をすると税金の還付がうけられる場合があります。例えば、次のようなケースが考えられます。
- 複数の証券口座で売買して、損失が出た口座と利益が出た口座がある場合
- 配当金を総合課税で申告して累進課税による税率にする場合
- 配当金と売買譲渡損失を損益通算する場合
- 本年度の売買譲渡損失を3年間の繰越控除する場合
- 基礎控除や生命保険料控除などの剰余控除がある場合
各項目の詳しい説明は省きますが、特定口座で源泉徴収していても確定申告をした方が得になる場合があるということです。
では、還付をうけるために、とりあえず取引している証券口座を全部申告すればいいかといえば、そうではありません。
必要のない源泉徴収された特定口座を確定申告することが、デメリットになる可能性もあります。
特定口座を確定申告することで合計所得が変わる
注意しなければいけないのは、確定申告することで合計所得が変わるということです。
合計所得金額|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm
合計所得とは、個人・法人の所得の合計金額です。課税される金額にも関わってきますが、それ以外にも関わってくる場合があります。
下記は国税庁のサイトの一部抜粋ですが
(注) 非課税所得や次の(1)から(5)のような所得は配偶者控除が受けられるかどうかを判定する場合の合計所得金額から除かれます。
(中略)
(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
参照元
配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm
とあります。
特定口座で源泉徴収すれば合計所得に株の利益は加算されませんが、確定申告をすることで株の利益も合計所得の一部として加算されるという事ですね。
合計所得が変わると困る事例
では合計所得が増加すると次の内容で不都合が生じる恐れがあります。
- 配偶者控除や扶養控除の判定
- 国民健康保険加入者の保険料
合計所得が増加することで配偶者控除や扶養控除から除外されたり、国民健康保険料の算定額の増加リスクが生じます。
一部の特定口座だけを確定申告して合計所得を抑える
合計所得を増加させないためには、株の利益は特定口座で源泉徴収して、確定申告をしない方が良いということです。
ですから、還付のために確定申告をしたい場合は、全ての証券会社の特定口座を申告するのではなく、還付のために必要な特定口座だけを申告すれば良いというわけです。
複数の特定口座と確定申告する口座の事例
例えば、3つの証券会社で次のような損益が発生したとします。
- A証券の特定口座(源泉徴収あり)で100万円の利益
- B証券の特定口座(源泉徴収あり)で50万円の利益
- C証券の特定口座(源泉徴収あり)で30万円の損失
上記の場合で、各証券会社の損益通算を考えた場合の確定申告はどうすればよいでしょうか。
B証券とC証券を確定申告して、A証券は確定申告しなかった場合
B証券の利益からC証券の損失を差し引くと20万円の利益になります。
この場合、B証券で50万円分の利益に対しての税金を払っていたので、C証券の30万円分の損失に対する税金が還付されることになります。ただし、20万円分の利益は合計所得として計上されることになります。
全ての証券口座を確定申告した場合
全ての口座を申告した場合は、A証券とB証券の利益からC証券の損失を差し引くことになります。
その場合も30万円分の利益に対する税金の還付になりますが、重要なのは合計所得が120万円計上されてしまうことです。
国民健康保険の加入者であれば、必要のないA証券の利益を確定申告したために、その所得の分だけ国民健康保険料の負担が増加します。結果的に、還付金額よりも保険料の方が高くなるかもしれません。
【まとめ】確定申告する時は必要な分だけ申告しよう
このように、確定申告する証券口座の違いで大きな影響が生じる場合があります。特定口座で源泉徴収することで得られるメリットを活かすためには、必要最低限の確定申告をすることが重要です。