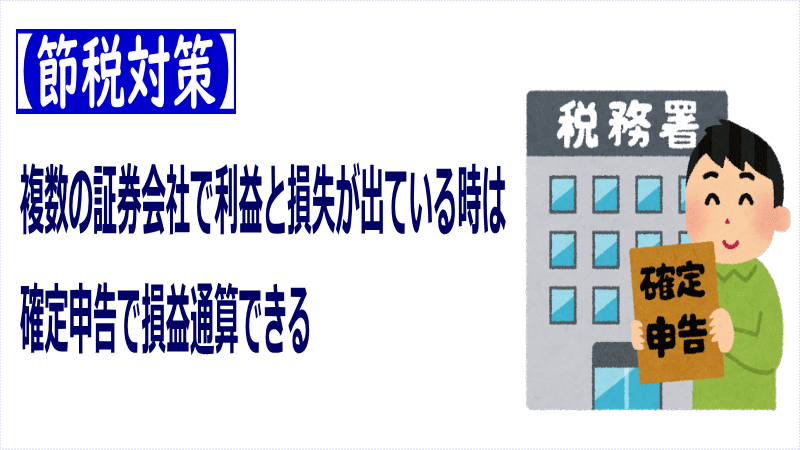「特定口座(源泉徴収あり)」で口座開設していれば、配当金・譲渡損益の所得の計算や税金の支払いを、証券会社が自動的に行うので確定申告をする必要はありません。しかし、特定口座は証券会社ごとに管理されているため、複数の証券会社で株の運用を行っている場合、必要以上に税金を納めているかもしれません。
特定口座(源泉徴収あり)の仕組み
「特定口座(源泉徴収あり)」の証券口座では、株の配当金の総額や売買譲渡損益、税金の計算は証券会社が自動的に行います。さらに証券会社が源泉徴収という形式で納税するため、個人投資家が確定申告する必要はありません。
特定口座では、配当金の総額と譲渡損益から売買にかかる手数料等を差し引いた金額を所得として、20.315%(所得税・復興特別所得税・住民税)の税率になります。
特定口座内で、配当金と譲渡損益で100万円の利益が出ていたら、約20万円が源泉徴収されることになります。
特定口座は証券会社ごとに管理されている
また、特定口座は証券会社ごとに管理されています。A証券ではA証券の特別口座、B証券ではB証券の特別口座となっており、それぞれの証券会社同士がその口座の情報を共有しているわけではありません。
そのため、複数の証券会社で株を保有して配当金を受け取ったり、売買で利益が出た場合には、それぞれの特定口座で源泉徴収が行われます。
利益と損失を特定口座で源泉徴収するとどうなる?
例えば、A証券で100万円の利益が発生し、B証券で80万円の損失が発生した場合、特定口座で源泉徴収していると、支払う税金はいくらになるでしょうか。
この例では、A証券で約20万円が源泉徴収されます。B証券では損失が発生しているので、源泉徴収はされません。
A証券とB証券を合算すれば利益は20万円ですが、源泉徴収された税金も約20万円になり利益が無くなりました。
特定口座で源泉徴収する場合には、各証券会社で納税されるために、このような理不尽なケースが生じることがあります。
源泉徴収されても確定申告すれば損益通算が可能
このような特定口座による過剰な源泉徴収を修正するためには確定申告が必要になります。
確定申告をすることで「A証券では100万円の利益が出ていますが、B証券では80万円の損失が出ていますよ」と申告することができます。つまり、実際に支払うべき税金は約4万円だと修正することになります。
そうする事で、A証券で源泉徴収された20万円のうち16万円が還付されます。※住民税・復興特別所得税・住民税を合算して
3社以上でも損益通算の仕組みは同じ
3社以上の証券会社で取引している場合でも同じ仕組みで損益通算が可能です。
- A証券・・100万円の利益
- B証券・・50万円の利益
- C証券・・120万円の損失
となっている場合に全ての証券会社の特定口座による損益を確定申告すれば、「100+50-120=30」になるので実際の利益は30万円であったことを申告します。
その結果、C証券の損失分の約24万円の還付が受けれられます。
複数の特定口座を損益通算する場合の注意点
別の証券口座で生じた株の損益は、確定申告で損益通算することが可能ですが注意点もあります。それは確定申告することで合計所得金額が変わるということです。
合計所得金額|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm
確定申告で損益通算した結果に生じた利益分だけ合計所得金額が増加します。合計所得金額は、配偶者控除や扶養控除の判定や国民健康保険加入者の保険料の計算にも関わってくるため、還付金額よりもそれらによる負担の方が大きくなるリスクがあります。
特定口座で源泉徴収している状態では、合計所得金額には影響がありません。
損益通算で合計所得が変わる事例
損益通算することで合計所得が変わる事例を挙げてみます。
- A証券・・300万円の利益
- B証券・・10万円の損失
上記のような場合に、損益通算のために確定申告をすると、A証券で源泉徴収された約60万円の税金のうち、B証券の損失10万円が損益通算されて約2万円還付されます。
しかし、確定申告した事によって合計所得は290万円多くなることになります。国民健康保険料の加入者であれば、所得が290万円増加するので保険料は還付金以上に高くなる可能性があります。
社会保険は合計所得に影響を受けない
会社の社会保険に加入している場合、社会保険料は標準報酬月額(給与など)を基に決定されます。
そのため、株の利益を確定申告して合計所得金額が増加しても、保険料は変わらないと考えられます。
ただし、加入する団体によっては保険料の算定方法が異なるかもしれません。損益通算する場合は加入している社会保険の窓口に問い合わせた方がいいと思います。
【まとめ】特定口座(源泉徴収あり)の制度を上手に使い損益通算をしよう
損益通算は複数の証券口座で取引している個人投資家にとっては必要な知識です。しかし損益状況によっては、還付金以上に国民健康保険料が高くなるなど、損益通算しない方が得になる場合もあります。
そのため、損益通算のために確定申告をする際には、合計所得の影響を検討する必要があります。