今回は私の確定申告の事例ということで、2018年に実際に株の利益を確定申告して、所得税の還付を受けた話です。
※確定申告は個々人で適用される控除や還付条件が大きく変わります。そのため、一例として読んでいただきたいと思います。
特定口座で納税しても確定申告で還付を受けられる
私は、株式投資で得た利益を主な収入として生活している兼業投資家です。セミリタイアというライフスタイルでもあります。
証券口座は「特定口座(源泉徴収あり)」を利用しているため、確定申告では株式投資による損益は申告しなくても構いません。
※「特定口座(源泉徴収あり)」は、証券会社が自動的に株の売買損益や配当金にかかる税金を計算、徴収してくれる仕組みです。
特定口座で徴収される税金は、売買益や配当金に対して一律で20.315%が徴収されます。所得税、復興特別所得税、住民税です。
特定口座を利用しても確定申告で還付が受けられる
しかし、特定口座で納税した所得税にしても、他の所得や適用される控除によっては還付を受けることができます。そのためには確定申告をする必要があります。
特定口座を利用していても確定申告することで適用される控除
私が確定申告で受けられた株式投資の利益にかかる所得税に適用される控除は以下の通りでした。
配当控除
配当控除は配当金にのみ利用できる控除です。課税総所得金額が695万円以下の場合に配当控除を利用することで税金が低くなります。
基礎控除
基礎控除では所得に対して48万円の控除(2024年1月時点)が受けられます。そのため、株式投資でしか所得がない場合などは、特定口座(源泉徴収あり)であっても、確定申告することで基礎控除の適用が受けられます。
社会保険料控除
社会保険料控除は、支払った国民健康保険や国民年金の額に対する控除です。こちらも特定口座(源泉徴収あり)であっても、確定申告することで控除が受けられます。
株の利益を確定申告した事で10万円の所得税が還付された
私が確定申告により受けられた株式投資の税金に対する還付金額は105,839円でした。
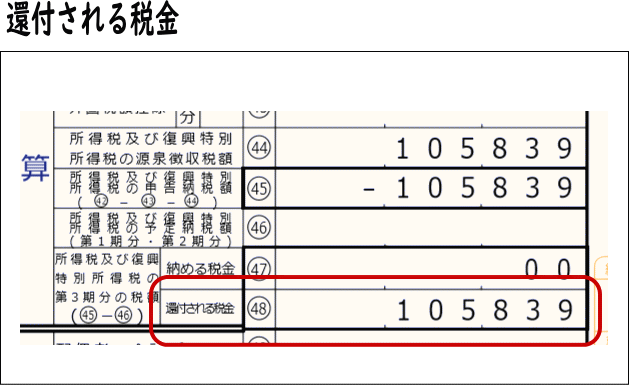
当時の私の株式投資以外の収入には、副業であるアルバイトの給与所得がありましたが、それ自体は給与所得控除以下の金額だったため、他に利用できる控除が全て残っていました。
住民税の申告不要制度は2023年以降は使えない
2018年の確定申告では、住民税において株式投資に関する所得だけを申告不要とすることができました。そのため、所得税については特定口座の申告を行い、住民税では申告不要を選択しています。
しかし、2023年分以降の確定申告では、住民税の申告不要制度は無くなります。そのため、株式投資でかかる所得税だけを確定申告で還付することは出来ません。
そのため、住民税でも同じ内容で確定申告をすることになります。
国民健康保険の加入者は還付で損をするリスクも
国民健康保険の保険料は、住民税における所得を基に算出されます。そのため、還付のために、株式投資の所得を確定申告する事で、住民税で申告する所得も増えることから、国民健康保険料の値上がりに繋がります。
そのため「還付は受けられたけど、それ以上に国民健康保険料の値上がりが大きかった」というリスクも十分に考えられます。
ですから、2024年以降、私のような国民健康保険の加入者には、特定口座(源泉徴収あり)を還付目的で確定申告するメリットは少ないかもしれません。
※この記事は私の経験によるものですが専門家ではありません。この記事の内容により不利益を被った場合でも一切の責任はとれませんので、確定申告をする際には、税務署や専門家、各自治体にご確認ください。
