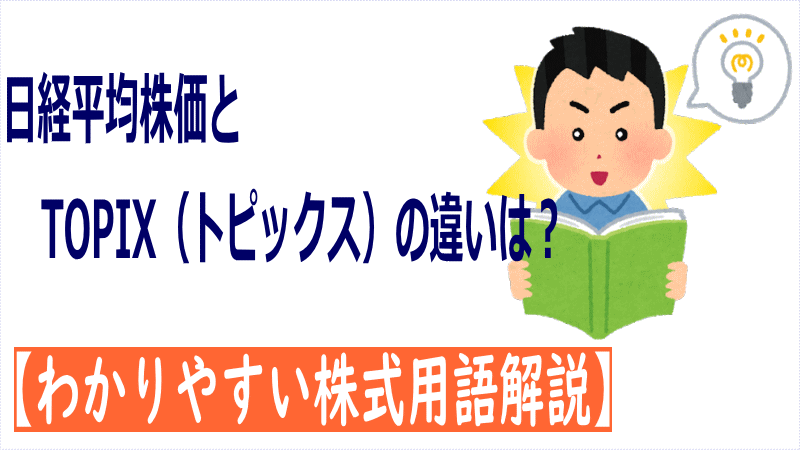本記事では日本株式市場の代表的な指数である日経平均株価とTOPIX(トピックス)の違いについて解説します。
日経平均株株価とTOPIXの違い
まず初めに、次の表が日経平均株価とTOPIXの大まかな違いです。
| 内容 | 日経平均株価 | TOPIX |
|---|---|---|
| 採用銘柄 | 東証プライム市場225銘柄 | 東証プライム市場全銘柄 |
| 計算方法 | 単純株価平均を補正 | 1968年の時価総額を基準 |
| 単位 | 円・銭 | ポイント |
| 提供元 | 日本経済新聞社 | 東京証券取引所 |
※東証の市場改編により、TOPIX採用銘柄は2025年にかけて段階的に移行中
日経平均株価とは
日経平均株価は日本の株式市場を代表する株価指数で、日本経済新聞社が東証プライム市場に上場する銘柄のうち225銘柄を対象として算出しています。
日経平均株価は、日本を代表する企業の株価の値動きを表していますので、国内外の投資家にもっとも重視されています。
日経平均株価の計算方法
日経平均株価を算出するための計算式は以下の通りです。
- 各構成銘柄の採用株価=株価×株価換算係数
- 日経平均株価 = 構成銘柄の採用株価合計÷除数
「株価換算係数」や「除数」など見られない言葉が並びますね。この計算式から算出される日経平均株価は、公式では次のよう解説されています。
日経平均株価は、株価換算係数で調整した構成銘柄株価の合計金額を、「除数」で割って算出します。除数は株価平均を算出する際に、市況変動によらない価格変動を調整し、連続性を維持するための値です。
引用元:指数情報-日経平均プロフィル
日経平均株価の採用銘柄
指数算出の対象となる225銘柄は流動性・業種セクターのバランスを考慮して、日本経済新聞社が選出します。また、定期的に銘柄入替を行うことで株式市場の動向を敏感に伝えます。
次の銘柄は代表的な日経平均株価の採用銘柄です。(2022年10月)
- トヨタ自動車
- 伊藤忠商事
- ファーストリテイリング
- 日本製鉄
- 大林組
- コマツ
- 川崎重工
- 三菱地所
- JR東日本
- 日本郵船
日経平均株価に採用されている銘柄は公式サイト「銘柄一覧ー日経平均プロフィル」から確認できます。
TOPIX(トピックス)とは
TOPIX(トピックス)は東証プライム市場の全銘柄を対象として、同取引所が算出・公表している株価指数のことで東証株価指数とも呼ばれています。※東証の市場改編により2025年1月まで順次移行中
TIPIXは1968年1月4日の東証第一部上場株の時価総額を100として算出しています。
東証プライム市場の全銘柄を対象としているため、日経平均株価と比べると特定の株の影響を受けにくい指数です。
TOPIX(東証株価指数)の計算方法
TOPIXを算出する計算方法は次の通りです。
TOPIXの基準日は1968年1月4日です。
日経平均株価とTOPIXの価値
日経平均株価は特定の銘柄から算出されるのに対して、トピックスは幅広い銘柄を対象に算出されます。しかし、単純に採用銘柄が多いからTOPIXの方が価値があるかと言えば、そうではありません。
グローバルな視点ではTOPIXより日経平均株価が重視されます。日本の代表的な銘柄を採用されている日経平均株価の方が国際的な影響力が大きいと考えられるからでしょう。これは、30銘柄から構成される米国ダウ平均と同じ理屈です。
逆に、プライム市場全体の動向を知る上では、TOPIXは頼もしい指標です。日経平均株価が上昇しているのに、東証プライム市場の保有株の動きが鈍く違和感がある時はTOPIXの動きに注目すると良いでしょう。