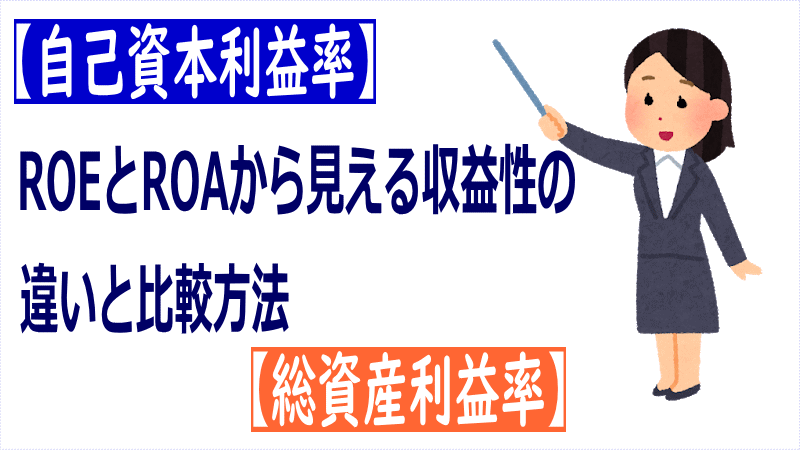企業の利益率を測るためのファンダメンタルズ分析指標、「自己資本比率(ROE)」と「総資産利益率(ROA)」の違いや特徴、使い方を解説します。
自己資本利益率と総資産利益率の計算式
それぞれの計算式は次の通りです。
- 自己資本利益率=当期純利益÷自己資本(株主資本)×100%
- 総資産利益率=当期純利益÷総資産×100%
これらの計算式の違いは分母だけです。自己資本と総資産の違いを除けば、同じ計算式になることがわかります。
※自己資本利益率は「株価収益率(PER)÷純資産倍率(PBR)×100%」でも求められます。
自己資本と総資産
自己資本と総資産は、次のような意味があります。
自己資本とは
自己資本は返済義務のない資本のことをいいます。
貸借対照表などでは、資本金や利益剰余金、資本剰余金などが自己資本であり、これらは返済義務のない会社の資本です。
総資産とは
総資産は、会社が保有している資産の合計です。例えば、現金・預金、売掛金、土地・建物、機械設備などです。
これらの総資産は、必ずしも自己資本として保有・購入しているものだけではありません。銀行などからの借入金や、借入金で購入したものも含めて総資産になります。
資本と資産の違い
資本と資産の違いは、貸借対照表の左右どちら側かの違いです。
貸借対照表では左側に資産、右側に他人資本(負債)と自己資本(純資産)が記載されています。大雑把に言えば「資産は負債と自己資本を合計した数字と一致する」ということです。
ファンダメンタルズ分析に必要な知識としては、このような理解でも十分だと思います。
自己資本利益率と総資産利益率の特徴と見方
自己資本利益率と総資産利益率は、どちらも企業の資金効率を測る指標です。しかし、各利益率の基準には次の違いがあります。
- 自己資本利益率は「株主から預かった資金」
- 総資産利益率は「負債も含めた運用資金」
自己資本利益率が高いだけでは必ずしも「買い」ではない
一般的に、自己資本利益率が高いということは、自己資本を効率的に運用していると考えることができます。当然、投資家にとっては自己資本を効率的に運用する企業は魅力的ですからROEは高いほど良いと言えます。※2023年の上場企業のROEの平均は9%程度
しかし、総資産利益率も知ることで、ROE(自己資本利益率)だけでは判断できないことがわかります。
ROE(自己資本利益率)が高く、ROA(総資産利益率)が低い
例えば、ROE20%、ROA2%の企業の株価はどう判断されるでしょうか。
ROE20%は上場企業平均9%を大きく超えて高水準と言えます。しかし、ROA2%は優良企業の目安とされる5%を大きく下回ります。
自己資本からすると優良企業であるように見えますが、総資産からすれば運用効率は高くありません。さらに言えば、負債の割合が極端に高いことから財務的にもリスクがあります。
※自己資本が100とすると利益が20、20の利益を出すための総資産は1000という事になり、他人資本(負債)は900になります
このように、ROE(自己資本利益率)だけでは見えないことも、ROA(総資産利益率)を見る事で判断できる事例もあります。
【まとめ】
効率よく資金を運用する会社は、海外投資家からも注目されるために、ROEとROAは日本株式市場においても無視できないファンダメンタルズ分析の指標です。
この二つの分析指標の違いと特徴を知ることで、より精度の高い投資分析が可能になります。