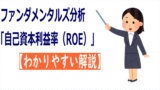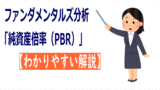今回はファンダメンタルズ分析の1つ「総資産利益率(ROA)」について解説します。
資金効率を測るファンダメンタルズ指標として自己資本利益率(ROE)がありますが、それだけでは不十分な一面もあります。
総資産利益率を併用することで、より正確な企業の資金効率や財務的健全性を分析することができます。
総資産利益率(ROA)とは?
総資産利益率「ROA(Return On Assets)」は総資産を基準に収益効率を測る指標です。
総資産利益率の計算式は「ROA=当期純利益÷総資産×100%」です。
次の2社を総資産利益率から投資判断してみましょう。
- A社:純利益2億円÷総資産10億円×100=総資産利益率20%
- B社:純利益2億円÷総資産20億円×100=総資産利益率10%
総資産利益率はA社が20%、B社が10%であるため、A社の方が資金効率が良いと判断できます。
総資産と自己資本の違い
総資産利益率(ROA)と自己資本利益率(ROE)の違いは、総資産と自己資本のどちらを基準に利益率を計算するかの違いです。※「総資産=自己資本+他人資本」
他人資本とは銀行からの借入など返済義務がある資本です。対して自己資本は株主などから調達した資本金や利益の剰余金など返済義務がない資本です。
- 総資産利益率(ROA)は返済義務のある資本も含めての利益率
- 自己資本利益率(ROE)は返済義務のない資本の利益率
総資産利益率(ROA)の目安
自己資本利益率の解説で「ROEが8%~10%以上が優良企業の目安」と言いましたが、総資本利益率は他人資本も含めて計算するため自己資本利益率より低い数値になるのが一般的です。
総資産利益率(ROA)の注意点
自己資本利益率に比べて極端に総資産利益率が低い場合には、財務的なリスクが潜んでいる可能性もあります。
例えば、ROEが10%なら一見すると優良企業ですが、ROAが1%しかないのであれば他人資本の比率が自己資本の9倍になります。この場合、過剰な借り入れ金による返済リスクを考慮する必要があるでしょう。
同じROA10%でも次の2社では資産構成は大きくことなります。
- A社:自己資本8割・他人資本2割
- B社:自己資本2割・他人資本8割
A社では他人資本は自己資本の1/4ですが、B社では他人資本が自己資本の4倍もあります。総資本利益率は同じでも、財務健全性が高いA社と成長力が見込まれるB社では性質は大きくことなります。
【まとめ】ROAとROEの両方から投資分析することが大切
資金効率は、企業のポテンシャルを見極めるポイントの一つです。そのため、資本の効率性を示す総資産利益率(ROA)は、重要なファンダメンタルズ指標です。
ただ、総資産利益率のみで企業の良し悪しを判断することは出来ません。自己資本利益率(ROE)や株価収益率(PER)、純資産倍率(PBR)なども参考にして、総合的に投資判断をすることが大切です。