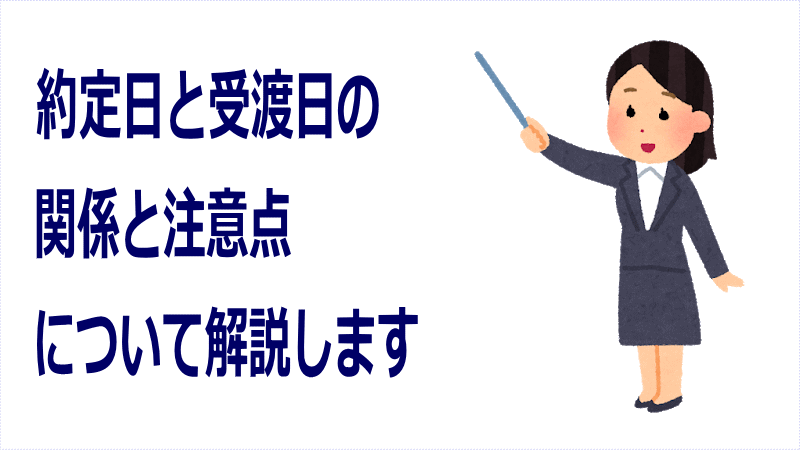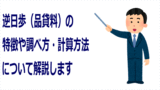株式投資では「約定日(実際に売買があった日)」の2営業日後に「受渡日(名義上株券が受け渡される日)」があります。
この約定日と受渡日の違いは、配当金や株主優待の権利を得るタイミング等で重要なポイントになります。
本記事では「約定日」と「受渡日」の違いや注意点について解説します。
約定日と受渡日の関係
「約定日」とは、”実際に”株式投資で株を売買した日のことです。それに対して、「受渡日」は”名義上”株式を購入者に譲渡される日のことです。
- 約定日・・株を売買した日
- 受渡日・・名義上株の譲渡がある日
約定日と受渡日の関係は、証券用語の解説では「約定日から起算して3営業日後が受渡日」と表現されています。
「起算」とはその日を含めてという意味ですから簡単に言えば「約定日の2営業日後が受渡日」ということになります。
土日や祝日を挟まない約定日と受渡日
例えば、祝日のない週の月曜日に株が約定すれば、2営業日後の水曜日が受渡日になります。
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 |
|---|---|---|---|
| >約定日 | 1営業日後 | 受渡日(2営業日後) | 3営業日後 |
約定日と受渡日の間に土日や祝日がある場合
約定日と受渡日は営業日で2日ズレるので、土日や祝日は考慮しません。
例えば、祝日のない木曜日が約定日の場合には、翌週の月曜日が受渡日になります。
| 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 |
|---|---|---|---|---|
| 約定日 | 1営業日後 | 休日 | 休日 | 受渡日(2営業日後) |
もし、月曜日が祝日の場合には、受渡日はもう1日ずれて、翌週の火曜日が受渡日になります。
| 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 約定日 | 1営業日後 | 休日 | 休日 | 休日 | 受渡日(2営業日後) |
この約定日と受渡日の関係が株式投資をする上で、重要なポイントになるのは次のようなイベントがあるからです。
配当金や株主優待に係る約定日と受渡日
株主は年に1~2回程度、配当金や株主優待を受け取ることができます。
実施回数や有無は企業によって違いますが、配当金や株主優待を貰いたい場合には、「特定の日」にその企業の株主でいる必要があります。
その「特定の日」を権利確定日と言い、決算日や中間決算日が権利確定日になるのが一般的です。
例えば、3月末決算企業の場合は、3月31日が決算日であり権利確定日になります。ちなみに中間決算は9月30日ですね。※月末が休日なら前営業日が権利確定日
では、3月末決算の企業の期末配当と株主優待を手に入れるには、いつ株を保有していればいいのでしょうか?
3月末の期末配当や株主優待を受け取るための約定日と受渡日
期末配当と株主優待を貰う条件は、「決算日の大引けに株主名簿に名前が載っていること」です。
つまり、受渡日である3月31日に株主名簿に名前が記載されることが配当金や株主優待を受け取る条件です。
受渡日から約定日を逆算してみましょう。
3月31日が金曜日だった場合には、3月28日の火曜日を約定日の期限になり、その日の大引けに株を保有していなければいけません。
この約定日のことを「権利付最終日」や「権利付最終売買日」などと呼びます。
| 29(水) | 30(木) | 31(金) |
|---|---|---|
| 約定日 | 1営業日後 | 受渡日(2営業日後) |
| 権利付最終日 | 配当権利落ち日 | 権利確定日 |
約定日ベースでは配当を貰えるかどうか決定する日を以下のような呼び方をします。
年末の税金に関する調整に関する約定日と受渡日
株式投資の利益にかかる税金は、1月1日から12月31日までの損益で確定します。
年末最後の営業日を大納会(だいのうかい)と言いますが、12月30日(土日の場合は前営業日)が大納会にあたります。
大納会とその営業日に約定した株の損益は、受渡日ベースでは2営業日後であるため翌年分の損益として見なされます。
ですから、損益調整のための売買をするのであれば、受渡日ベースで年内に取引する必要があります。
年末に損益を調整する例
例えば、株の売買益が年間で100万円出ていたとします。その場合には、売買益にかかる税金は約20万円(20.315%)です。
しかし、その状態で40万円の含み損があり、その40万円の損失を確定すれば、売買益は「100万円-40万円=60万円」と少なくなります。
そういった場合に、含み損を抱えた株を売却して損失を確定するなら、大納会に売却しても損益が相殺されません。損益を調整するなら受渡日ベースで年内に売却しなければいけません。
2024年の大納会と受渡日の関係
2024年の大納会は12月30日月曜日です。2024年の大納会を受渡日にするためには、2営業日前の12月26日木曜日を約定日として、損失を確定する必要があります。
空売りの逆日歩(ぎゃくひぶ)に係る約定日と受渡日
逆日歩とは 、「制度信用取引で貸株残が増加し、売り建てる株が不足した時に売り方が支払うコスト」のことです。
簡単に言えば、空売りした人が株の調達コストを負担する仕組みです。
逆日歩は営業日だけでなく休日も発生します。つまり、「土日や祝日を跨いで株を空売りした場合は、その分も逆日歩が発生する」ということです。
この逆日歩も約定日ではなく受渡日ベースになるので、金曜日に株を空売り(約定)したとしても、土日の分はかかりません。
受渡日ベースで考えると「水曜日に株を空売りした場合には、土日2日分の逆日歩も余計に発生する」ことになります。※祝日を挟まない場合
つまり、逆日歩の計算は次のような理屈です。
- 約定日が水曜日の場合、受渡日で金曜日になる
- 受渡日が金曜日で持ち越す場合、土日を跨ぐことになる
- 3日分の逆日歩が発生する
そのため、逆日歩が高額になるような銘柄を水曜日に空売りするのは、普段よりもリスクが高くなることに注意しましょう。