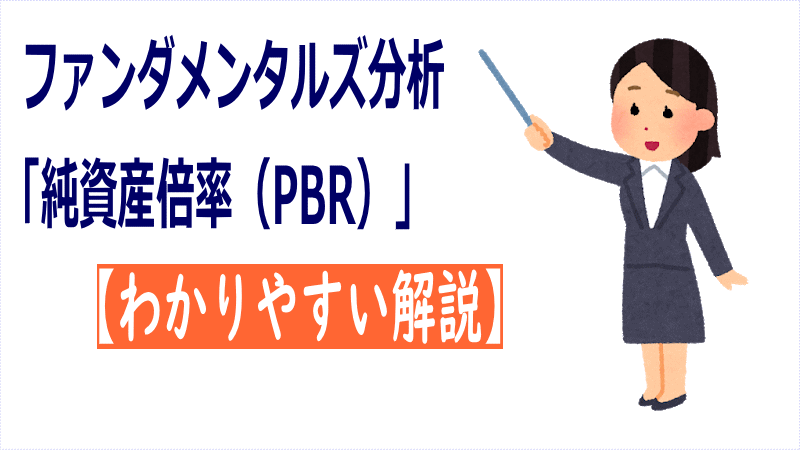ファンダメンタルズ分析とは、業績や財務と株価を比較して、株価の割安性、割高性を判断する方法です。今回は、代表的なファンダメンタルズ分析指標の一つである純資産倍率「PBR」について解説します。
純資産倍率(PBR)とは?
純資産倍率(PBR)は「会社の純資産と株価の関係」を表すファンダメンタルズ分析の指標です。PBRは「price book-value ratio」の略称になります。
純資産倍率(PBR)の計算方法
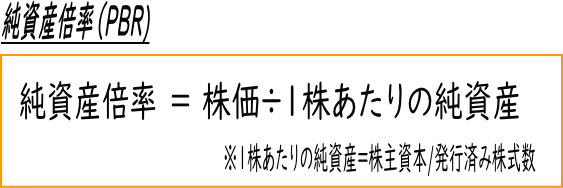
純資産とは、企業の資産から負債を差し引いたものです。つまり、資産の総額から負債の総額を引いた残りの価値を指します。
会社が解散すれば負債は債権者への返済義務がありますが、純資産は返済義務がありません。つまり、解散時には株主に還元されるため、純資産倍率は会社の解散価値を計る指標とも言われます。
PBR1倍なら株価は会社の純資産と同等
純資産倍率の計算式に当てはめると、PBRが1倍なら株価と1株あたりの純資産は同じ数字であると言えます。理論上は、PBR1倍なら会社が解散しても株主は純資産の還元を受けるため、損はしないことになりますね。
【注意】純資産の数字は会計上の数字
しかし実際にPBR1倍の会社が解散した場合、株主は株価と同等の還元を受けることはありません。純資産はあくまで会計上の数字です。
会計上の数字は現金化するための数字ではなく、資産である車を現金化しても会計上の数字と現金化した時に受け取れる金額は必ずしも一致しません。詳しくは後述します。
関連記事 株主資本と自己資本と純資産の違い
関連記事 自己資本と純資産の違い
純資産倍率(PBR)による投資判断
投資判断に用いられる純資産倍率は頼もしい指標の1つです。前述の通り、PBRが1倍なら、株価と1株当たりの純資産が釣り合う状態です。
ではPBRが1倍未満、1倍を超える場合に、投資家はどのように投資分析ができるでしょうか。
純資産倍率(PBR)が1倍未満の場合
純資産倍率「PBR」は数字が小さいほど株価が割安であると判断されます。つまり1倍を下回れば、1株あたりの純資産より株価の方が安いことになります。
例えば、株価が1000円でPBRが0.5倍なら、会計上は1株につき2000円の純資産を有することになります。
純資産倍率(PBR)が1倍より大きい場合
逆に、PBRは数字が大きいほど、株価は割高であると判断されます。
例えば、株価が1000円でPBRが4.0倍なら、会計上は1株につき250円の純資産を有することになります。株価1000円から純資産分の250円を差し引いた残りは、会社の将来性や会計上に現れない価値が株価に織り込まれていると考えることが出来ます。
純資産倍率(PBR)がなぜ1倍を割れるのか
「日本証券取引所グループが発表している統計資料」によると、東証プライム市場のPBR平均は1倍台前半で、ほぼ「純資産=株価」と言えるような水準です。PBRが1倍未満の会社も少なくありません。
その理由は、純資産倍率が必ずしも会社の解散価値と株価の関係にないのが主な要因です。
純資産はあくまで会計上の数字
純資産とは、企業の資産から負債を差し引いた「会計上の数字」です。そして、資産、負債についても同様です。
特に、資産には機械設備、車両、不動産などは、現金化すれば会計上の数字と価値が大きく乖離するものもあります。
もし会社が解散して、株数に応じて株主に残余財産を分配するとしても、現金化すればそれらの価値は大きく減少する場合があるという事です。
だから、PBRが1倍が実質的な解散価値ではないという事は注意しなければいけません。
あわせて読みたい 決算書の基本知識
純資産倍率(PBR)の特徴
純資産倍率(PBR)の数値には、次の傾向があります。
- 新興企業ほどPBRは高い
- 成長企業ほどPBRは高い
- 業績が安定している会社のPBRは低い
- 歴史のある会社のPBRは低い
純資産倍率(PBR)が高い会社の傾向
新興企業はPBRが高い
新興企業ほどPBRが高くなる傾向があります。利益剰余金が少なく先行投資が嵩むため、純資産より負債の割合が高いからです。
成長力のある会社はPBRが高い
また、成長力のある会社もPBRが高くなる傾向にあります。将来得られるであろう利益を見越して、投資家が株を買うからです。
そのため、東証プライム市場の銘柄のPBR平均は1.1倍ですが、東証グロース市場では3.6倍もあります。(2022年9月)
純資産倍率(PBR)が低い会社の傾向
歴史のある会社のPBRは低い
歴史がある企業は、それだけ利益余剰金が積み重なります。そのため、歴史がある企業は負債よりも純資産の割合が多くPBRが低くなる傾向があります。
業績が安定している会社のPBRは低い
業績が安定している会社はPBRが低くなる傾向があります。
業績が安定しているということは、逆に言えば成長性が乏しいとも言えます。そのため、投資家の将来性を見越した買いが入りません。
純資産倍率(PBR)の上手な見方
純資産倍率は、単純に数字の大小で投資判断をするだけでは、最低限の判別しかできません。PBRで効果的に投資判断するには次のポイントを抑えましょう。
業種別・市場別で比較する
ファンダメンタルズ分析は、業種平均、市場平均が全く違います。業種、市場によって成長性や収益力、財務内容の特徴が違うからです。
そのため、純資産倍率でも、特徴が大きく違う異業種間・市場で比較しても、参考にはなりません。純資産倍率の業種別・市場別に平均を確認した上で判断しましょう。
他の指標と併せて総合的な投資判断をする
PBRはファンダメンタルズ分析の代表的な指標ですが、あくまで純資産と株価の関係だけを表した数値です。そのため、PBRだけで株の割安、割高を判断することは安直です。
業績と株価の関係性を表す株価収益率「PER」など他のファンダメンタルズ分析も含めて総合的に判断することで、投資判断をより正確にすることが可能です。
貸借対照表を見る
貸借対照表では、企業の資産、負債、純資産の内訳が記載されています。その内訳を知ることで、詳細な企業の財務状況がわかります。
資産や負債のバランスで純資産倍率には現れない財務的なリスクや魅力が見つかるかもしれません。