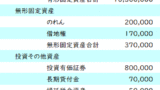流動資産と流動負債の勘定科目の意味や個人投資家が注意するポイントについて解説します。
流動資産の勘定科目
流動資産には現金や預金以外にも「一年以内に現金化することができるもの」が含まれています。ここで最初に登場した貸借対照表の流動資産を確認してみましょう。
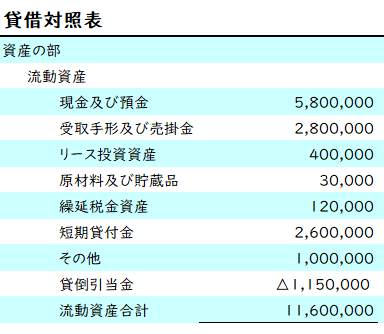
流動資産の勘定科目には次のような項目が並びます。
- 現金及び預金
- 受取手形及び売掛金
- リース投資資産
- 原材料及び貯蔵品
- 繰延税金資産
- 短期貸付金
- その他
- 貸倒引当金
どれも1年以内に現金化できる資産として計上されていますが、必ずしも貸借対照表の数字のまま現金化できるとは限りません。また、場合によっては現金化が難しい場合もあります。
例えば、勘定科目によって次のようなリスクが内在しています。
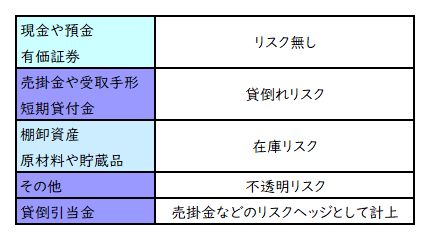
このように流動資産と言えども、必ずしも換金できるものばかりではないという事には注意が必要です。
例えば、棚卸資産や原材料、貯蔵品などはあくまで販売を目的とした資産ですから、売れ残りや使いきれない在庫などは処分されるリスクがあります。
会計上は資産として計上る棚卸資産ですが、計上額があまりに多い場合には実際の資産価値と会計上の資産価値が大きく乖離している可能性もあります。
また、売掛金や受取手形、短期貸付金などは相手の経営不振などから回収出来ないリスクを考慮する必要があります。
流動資産の例外「貸倒引当金」
流動資産の勘定科目の中で「貸倒引当金」だけマイナス計上されているのがわかります。
これは売掛金や受取手形、短期貸付金などが回収できないリスクがあると会社が判断した場合に計上されるものです。予め資産にマイナス計上することで、財務的リスクの調整を行っています。
流動負債の勘定科目
次は貸借対照表の流動負債の勘定科目を見てみましょう。
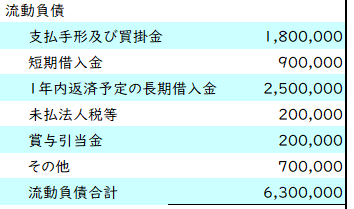
流動負債には次の項目があります。
- 支払手形及び買掛金
- 短期借入金
- 1年以内返済予定の長期借入金
- 未払い法人税等
- 賞与引当金
- その他
これらの勘定科目はすべて一年以内に支払いまたは納付する義務があります。
流動負債は流動資産に比べると勘定科目が少なくわかりやすいですが、こちらにも例外があります。それは「前受金」とよばれる勘定科目です。
上の貸借対照表には出てきていませんが、前受金は「サービスや商品に対して提供される前に支払われるお金」です。
つまり、まだ完全に納品や履行されていないものに対して、予め取引先から報酬の一部(または全部)を預かっている状態です。取引が完了するまでは、会社のお金ではない現金(流動資産)を預かっているために、流動負債側に前受金という形で計上されます。
前受金は流動負債として計上されていますが、納品が履行されれば売上の一部になりますので、他の勘定科目のように返済義務があるものではありません。
次回に固定資産と固定負債についてみていきましょう。