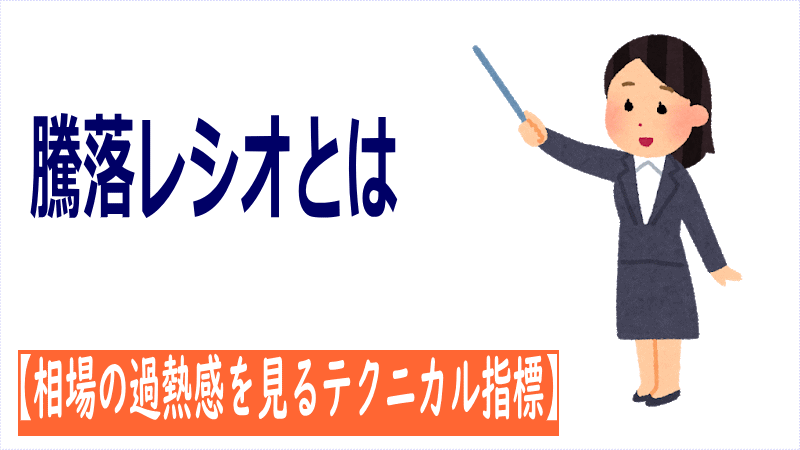騰落レシオは、値上がり銘柄数と値下がり銘柄数の比率から、市場の過熱感を測るテクニカル指標です。
シンプルな指標ながら株式市場全体の動向を見る事で、マクロ的な相場の先行きを予測することができ、多くの投資家に利用される指標の一つです。
本記事では騰落レシオの基本と使い方について解説します。
騰落レシオの基本
騰落レシオは市場の過熱感を測るテクニカル指標で、相場全体として「買われ過ぎ」なのか「売られ過ぎ」なのかを知ることが出来ます。
騰落レシオの計算式は非常にシンプルですね。
- 騰落レシオ100%・・値上がり銘柄、値下がり銘柄が同数
- 騰落レシオ100%より上・・値上がり銘柄数が多い
- 騰落レシオ100%より下・・値下がり銘柄数が多い
騰落レシオの期間
騰落レシオは1日ではなく、5日または25日平均で使われる事が一般的です。
- 5日騰落レシオ:5日間の値上がり銘柄数の合計÷5日間の値下がり銘柄数の合計×100
- 25日騰落レシオ:25日間の値上がり銘柄数の合計÷25日間の値下がり銘柄数の合計×100
市場の過熱感を測るためには、25日騰落レシオから判断されることが一般的です。
騰落レシオの過熱感のサイン
騰落レシオから相場の過熱感を測る時は
- 騰落レシオ120%以上:買われ過ぎ(天井圏にある)
- 騰落レシオ70%以下:売られ過ぎ(底値圏にある)
として判断されます。
つまり騰落レシオが120%以上なら「売り場」、70%以下なら「買い場」であると考えることが出来ます。
騰落レシオはシンプルでも信頼性が高い
騰落レシオはシンプルながら、信頼性の高い指標の一つです。
値上がり銘柄数と値下がり銘柄数の差は、買いたい投資家と売りたい投資家による綱引きのようなもので、相場の強弱を表す数字です。
その綱が一方に行き過ぎた場合には、そこから戻る力が強く働くというのが、騰落レシオの考え方です。
相場の転換点を見極める
「頭と尻尾はくれてやれ」という相場格言があります。
これは、自分の予想よりも株価が高く(低く)なることで、利益を取り切れなくても気にするなという格言です。
株式投資をしていると、トレンドの最後で想像以上に値上がり(値下がり)する現象を度々見かけると思います。
相場の過熱感が原因で、上昇や下落の最後には一時的に行き過ぎるというのは、珍しいことではありません。
そういった過熱感を見るのに、この騰落レシオという指標は効果的です。もちろん騰落レシオが120%や70%になったからと言って、すぐに相場が転換するとは限りません。
しかし、騰落レシオがその水準に到達したという事は、「一旦のトレンドが落ち着くタイミングが近い」と考えることが出来るでしょう。