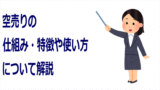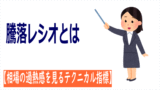相場の先行きを判断する指標の一つに「空売り比率」があります。
空売り比率は「売り注文の合計金額に占める空売りの合計金額の割合」を数値化した指標で、この数字が大きいほど、空売りしている投資家が多い事がわかります。
本記事では空売り比率の基本知識と使い方について解説します。
空売り比率の基本的知識
空売り比率は、相場の過熱感から「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を判断するテクニカル指標です。
空売り比率は、以下のように計算されます。
空売り比率が高いほど、売り注文全体の空売りが占める割合が多いことになります。
空売り比率が高いという事は、相場が下落すると予想している投資家が多い一方で、将来的には株は買い戻されるため上昇エネルギーにもなります。
空売り比率の調べ方
空売り比率は、日本証券所グループのサイトから調べることが出来ます。
外部リンク:空売り集計 | 日本取引所グループ

このページの中にあるPDFファイルを開くと、指定した日の空売り比率を知ることが出来ます。
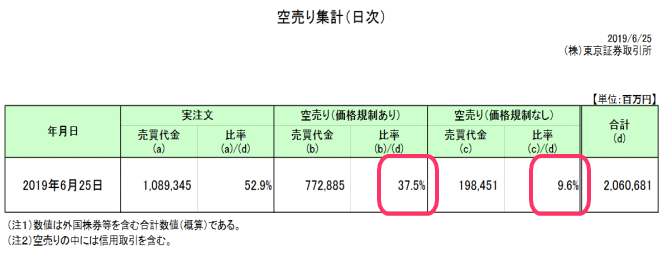
こちらは、日本証券取引所グループで確認できる空売り集計の表ですが、売り注文を以下のように分類しています。
- 実注文・・現物株の売りや信用取引(買建玉)の返済注文
- 空売り(価格規制あり)・・価格規制の伴った空売り注文
- 空売り(価格規制なし)・・価格規制の伴わない空売り注文
この中で、2つの空売りの割合を足したものが、空売り比率になります。
価格規制とは、空売りに設けられたルールのことで、トリガー抵触銘柄を51単元以上(5100株以上)1回の注文で行う場合に適用されます。
一般の個人投資家が一度に5100株以上の株を空売りすることは少ないと思いますので、「規制あり=機関投資家」「規制なし=個人投資家」くらいのイメージで良いでしょう。
上記の日にちは、「空売り(価格規制あり):37.5%」「空売り(価格規制なし):9.6%」なので、空売り比率は47.1%となります。
なお、価格規制(トリガー抵触銘柄)については以下の記事で詳しく解説しています。
空売り比率の基準はトレンドによる
空売り比率をみることで、投資家の相場に対するスタンスがわかります。空売り比率が高ければ相場に対して弱気、空売り比率が低ければ相場に対して強気であると言えるでしょう。
しかし、それも行き過ぎれば過熱感へと変わります。特に、空売り比率が高過ぎれば近い将来に空売りの買戻しが起こり、反発のキッカケになることもあります。
空売り比率の基準値
空売り比率の基準値は、中長期的な相場状況によっても異なります。2022年11月では空売り比率は40~45%程度が平均的な水準と言えるでしょう。
空売り比率が45%以上になると高く、50%以上になると高過ぎると考えることが出来ます。
空売り比率の推移を参考にする
相場状況によっても空売り比率の基準は変化するので、空売り比率は絶対的な数値ではなく、その推移を参考に過熱感を測るのが効果的だと思います。
また、騰落レシオも同じく過熱感を表す指標なので、騰落レシオと照らし合わせるのも効果的でしょう。
相場の動向、騰落レシオ、空売り比率の3つから、相場が過熱しているかどうかを判断することで、より精度の高い相場分析が可能になるでしょう。
空売り残高比率は別の数値
空売り比率と似た用語で「空売り残高比率」があります。空売り残高比率を空売り比率と呼ぶこともあるようです。
簡単に言えば、空売り残高比率はある銘柄の「出来高に占める空売り残の割合」です。似て非なる用語ですので混同しないように注意してください。