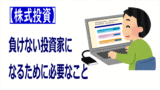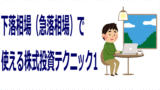多くの個人投資家が投資に失敗して退場を余儀なくされるのは急落相場で起こります。今回は、急落相場のリスク管理方法についてまとめました。
致命的な損失とは?
急落相場における最優先のリスク管理は「致命的な損失を避ける」ことです。そこで「致命的な損失」とはどういう事かというのを考えてみましょう。
「致命的な損失」には共通となる数値基準はありません。個人投資家によって、投資手法、技術、目的は違うからです。
そのため抽象的にはなりますが「二度と投資が出来ない(したくない)と思う損失」を具体的な数字で想像してください。
私の場合は、以下のような投資スタンスから致命的な損失を考えています。
このような投資スタンスのため、相場の急落時には全く損失を被らないというわけにはいきません。
そんな状況の中で、私にとっては「資産の50%以上を失ってしまうような投資」は「致命的な損失」であると考えています。
2000万円の運用資金のうち1000万円を失うような事があれば、現状の投資スタンスを維持するのが難しくなります。
致命的な損失は急落相場で起こる
致命的な損失の多くは急落相場で起こります。
相場が安定している状況で個別株が急落したとしても、下方修正や不祥事など株価急落の要因が明確であるために、対応することはそれほど難しくありません。見通しが悪いと判断すれば、損切りすれば良いからです。
しかし、相場全体が急落する際には原因や規模が不明瞭な場合も多く、個別株の急落に比べて判断が難しいという特徴があります。
そのため、業績の見通しに具体的な変化がない保有株を売るべきかの判断は想像以上に難しく、対応が遅れた時には「致命的な損失」になる可能性があります。
致命的な損失を避ける心得
致命的な損失による相場の退場さえなければ、急落相場の影響で損失が出たとしても、次の上昇相場へ繋げることが出来ます。
「致命的な損失を避ける」ためには、次の意識が大切です。
「相場の常識が変わった」ことを意識する
株式投資をしていると「大体このへんで下げ止まるだろう」とか「○○日移動平均線の水準に近づいてるから、そろそろ反発するだろう」と経験や知識によって、株価の推移を予測するようになります。
相場が安定している時は、そういう予測は難しくありません。そのため、安定相場が長期間続くほど、投資家は相場の先行きを予想する事に自信を持つようになります。
しかし、急落相場が始まると相場の常識は一変します。相場の急落時に、これまでなら反発していたような水準で買い増しをして、下げ止まらなくなって多くの含み損を抱えるといった悲劇は、急落相場で常識が変わったという認識が出来ないことが要因の一つとも言えます。
自分で底を判断しない
急落相場が始まったという事は、先に述べた「相場の常識が変わった」ということです。であれば、特に短期的に見た場合、「下落の底がどこになるのか」というのは容易には判断できません。
どれだけ下落したとしても相場の底を勝手に判断しないで、さらに下値があることを想定する必要があります。そのために、次のような考え方が大切です。
一時的に株価が戻っても第二波、第三波の急落を警戒する
急落相場では「大きな下落が複数回起こる可能性」があります。
最初の急落で、例えば日経平均株価が5%下落したとします。100万円分の保有株があり、指数に連動していれば5万円前後の損失は発生します。痛い損失ですが、この一回で急落が終わり元の相場に戻るなら、それほど怖いものではありません。
しかし、その急落が引き金となって複数回の大きな下落、時には歴史的な下落相場へのキッカケとなる可能性もあります。
相場の下落が複数回に分けて発生する理由
第二波、第三波が発生するメカニズムの一つは「株式の売買の主体は個人投資家でなく機関投資家である」からです。
個人投資家には「多少相場が悪くなって株価が下落したとしてもホールドしておけば良い」と考える人も多くいるはずです。含み損を放置したところで、実生活には仕事による収入があるので影響はありません。
しかし、機関投資家は投資の運用損益がそのまま企業の存続に繋がります。そのため、個人投資家よりもシステマティックな運用が求められます。
機関投資家の投資資金は相当なものですから、彼らが厳格なルールに則って保有株を損切り、もしくは利益確定として売却してきたらどうなるでしょう。
「売りが売りを呼ぶ展開になって、損切りしたくれも出来ない、あるいは想定以上に損失が加速する可能性がある」ということです。
そのような理由から、一度は株価が戻り基調にあったとしても、また新たに売ってくる機関投資家がいれば、大きな下落が繰り返し起こることになります。そういう動きが急落後の株価の反発に対しても異様に強い売り圧力の要因の一部になっているのです。
株は上昇時よりも下落時の方が動きは早い
株が上がる時にはみんなが利益を出している状態です。元々なかったものが上がり続けるのであれば、じっくり保有していれば良いし、どうしても資金が欲しいわけじゃなければ無理に買い上げる必要もありません。
しかし、下落していく過程では「自分の資産が無くなっていく状態」です。「元々無かったはずのものが増える時」よりも、「本来持っているものが失われていく時」の方が動きが早くなるのは、プロスペクト理論によっても明らかです。
このような急落相場におけるメカニズムを理解しておけば、株式投資で失敗して退場という最悪のケースは避けられるでしょう。急落相場のリスク管理こそ、投資を成功させる大きなカギとなります。