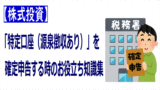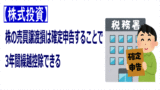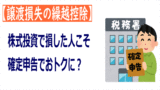株式投資においても、年末年始は大きな区切りになります。
その理由は「1月から12月の株式投資の累計損益から支払うべき税金が確定する」からです。そこで、今回は株式投資の税金を年末に効果的に節税するには、どうしたら良いのかを考えてみました。
株式投資にかかる税金は?
2019年末では株式投資にかかる税金は、所得税と住民税、それに復興特別所得税が加算されて、年間の利益に対して合計で20.315%が課税されます。年間で100万円利益があるなら、大体20万円くらいが税金として引かれます。
- 所得税:15%
- 住民税:+5%
- 復興特別所得税:0.315%
証券会社の特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合には、売買の都度、利益が出たら税金が差し引かれ、損失が出たら税金が還付されています。
株式投資の税金で注意するポイント1:含み益・含み損
含み益・含み損は、確定損益ではありません。そのため、いくら含み益や含み損があろうと、その株を売却しない限りは税金はかからないし、還付もされません。
含み益含み損による税金の調整方法
含み益や含み損のある株を上手なタイミングで売却することで、売買益を調整することができます。
年末時点で株式投資で利益が発生している場合
年末時点で株式投資によって利益が出ている場合は、含み損のある銘柄を一旦売却すれば、確定利益を減らすことができます。
年末時点で株式投資で損失が発生している場合
年末時点で株式投資によって損失が発生している場合は、含み益がある銘柄を一旦売却することで、利益に対する税金の一部または全部をこれまでの損失で相殺することができます。
株式投資の税金で注意するポイント2:約定日と受渡日
2つめの注意するポイントは「約定日と受渡日」です。株式投資においては、売買した日を約定日といい、株券の名義上の移行日を受渡日と言います。
※2019年7月15日までは約定日から3営業日後が受渡日です。2019年7月16日以降は受渡日が1日早まり、約定日の2営業日後に変わります。
2019年の最期の受渡日と約定日
2019年は12月30日(月曜日)が市場の開いている最後の日(大納会)ですから、受渡日が12月30日になるように計算します。
約定日は2営業日前ですから、遡って12月26(木曜日)大引けまでに売買するのが、事実上は2019年最後の取引日となります。