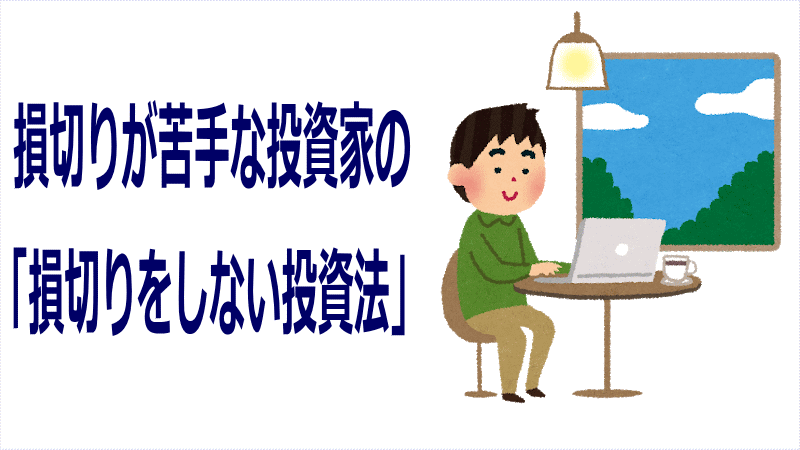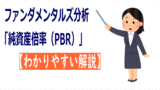このブログでは、株式投資のリスク管理における「損切り」の重要性について、いくつかの記事で解説しています。
しかし、理屈ではわかっていても、潔く損切りできる個人投資家は少ないと思います。実は、私自身も損切りをすることが、かなり苦手な個人投資家です。
そこで、本記事では「損切りを使わない投資法」について解説します。
損切りとは
損切りは、含み損のある保有株を売却して損失を確定する行為です。
損切りがリスク管理において大切な行為である理由は、含み損を抱えたまま何もしないと次の弊害が発生するからです。
- 資産が拘束される
- 含み損を抱えた株が戻る保証はない
- 含み損を抱えた株がさらに下落する可能性もある
- 他の株を買えないので投資機会を逃す
損切りが出来ない投資は資金効率が悪い
これらの事から、損切りをしない投資は効率が悪いことは間違いありません。
しかし、何でもかんでも損切りしてしまえば投資で勝てるかと言えば、そんな事もありません。損切りした株がその後、反発してしまったという経験は誰にでもあるはずです。
その経験が増えるほど、損切りを躊躇する気持ちが強くなるというのは、個人投資家のあるあるではないでしょうか。
損切りしない投資に切り替える
損切りは大切なルールの一つですが、適切な損切りを続けるのが難しいことも事実です。
であれば、「損切りをしない投資法」を身につければ、損切りに悩む頻度は減るはずです。
損切りしない投資のルール
私が実践している、損切りをしない投資法は次の方針に基づいたものです。
- 長期投資覚悟で利益になるまで売らない
- 1回の購入株数は最小限でナンピン買い前提
- 低PER・PBRの株を投資対象にする
- 株価が半分になった場合を想像する
- 買い増し(ナンピン買い)分は利益が出たら決済
- 明らかな失敗では損切りは必要
長期投資覚悟で利益になるまで売らない
買った株は利益が出るまでは売らないというのが、この投資法の基本になります。
但し、株価が買い値よりも高くなるまで売れないわけではありません。長期投資であれば、配当金や株主優待が貰えます。
例えば、配当性向3%の株に投資したとすれば、株価が年間に3%下落しても損益は0になるわけですから、5年間保有していれば15%の下落までなら許容範囲ということになります。
1度の購入株数は最小限でナンピン買い前提
損切りをしないということは、買った株が大きく下落しても致命的な損失にならないような資金管理が必要になります。そのため、「1度の購入株数は最小限に抑える」必要があります。
私の場合には、1銘柄に100万円の投資資金を投入するつもりなら、1回の購入額は約5万円です。
そして、株価が5%下落するごとに5万円ずつ買い増しして、平均買付単価を下げていきます。
業績が黒字なら会社の資産が減少することはないので、株価が下落したとしても、必ずどこかで下げ止まります。
低PER・PBRを投資対象にする
損切りをしない投資法では、株価が下落することを想定した投資を行う必要があります。
そのため、株価の下落余地は重要なポイントになります。下落余地が大きいほど、買い増しする回数や金額が増加していくので資金効率が悪くなります。
また、長期投資も視野にいれた投資であるために、配当利回りも重要な投資要素になり、配当利回りが高い低PER・PBR銘柄を投資対象にする方が良いでしょう。
株価が半分になった場合を想像する
手堅く投資したつもりでも失敗するのが投資です。
損切りを行わないのであれば、株価が半分になることも十分に考えられるわけですから、その時の資産状況がどういう状態で、自分の心理的な負担がどれくらいになるのかというを考えなければいけません。
買い増した株は利益が出たら決済
買い増した株は利益が出たら、早めに利益確定するのも、この投資法の重要なポイントです。
投資格言に損失は小さく利益は大きく取ろうという「損小利大」がありますが、損切りで損失を最小限に抑えることが出来てこその格言です。
損切りをしないのであれば、買い増し分は小さい利益であっても利益確定していく方が効率的です。
もし、利益確定した後にまた株価が下落したとすれば、再び買い戻し平均買付単価を下げていくことが出来ます。
明らかな失敗では損切りが必要
損切りをしない投資法とは言いましたが、明らかな失敗には損切りが必要です。
- 大幅な業績下方修正で今後も回復が見込めない
- 会社の不祥事
- 経営方針の改悪
例えば、上のような明らかに将来性がない状態に陥るようなら損切りしましょう。このような状態でも損切りしないのであれば、それは投資法ではなく何も考えていないだけです。
損切りしない投資法のメリットとデメリット
私自身は、ここ15年ほどは損切りしない投資で株式投資を行っています。損切りに迷う事は少なくなりましたが、デメリットもあります。
その中でも大きなデメリットは資金効率が限定されることです。
私がこの投資法を用いてからの利回りは、年間で20~50%くらいです。つまり1000万円の投資資金に対して年間で200万円から600万円くらいの利益が目安になります。(日経平均株価が年間で変動しなかったと考えて)
損切りの技術がある投資家が、徹底した損切りを行い、積極的に変動の大きい銘柄に投資した場合には、年間の利回りは100%以上になることも珍しくありませんので、資金効率が良いとは言えません。
そのため、損切りの技術やルール設定に自信がある個人投資家にとっては、損切りをしない投資法は資金効率が悪いでしょう。
損切りしない投資は安定志向の投資に適している
ただ、損切りの技術に自信がない個人投資家には、長期的に資産を運用し安定した投資基盤を作る「損切りしない投資法」は効果的な手法だと思います。
含み損を抱えても平均買付単価を下げつつ、高い配当利回りを受け取るという単調な売買ですが、その分、余計な投資判断が必要ないために、ある意味機械的な投資が可能とも言えます。
損切りしない投資法の一例
損切りをしない投資法を用いた私の取引の一例ですが、1400円で買った株が1000円になったことがあります。普通なら含み損を抱えた状態になりますが、細かい買い増しと利益確定、そして配当金を受け取ることで、総合的にはその銘柄で利益を出している状態です。
期間的には3年ほど保有しているので、決して効率が良いわけではありませんが、普通なら損切りしたであろう株で利益を出しています。
損切りが苦手ならこういう投資法もあるということを紹介しました。